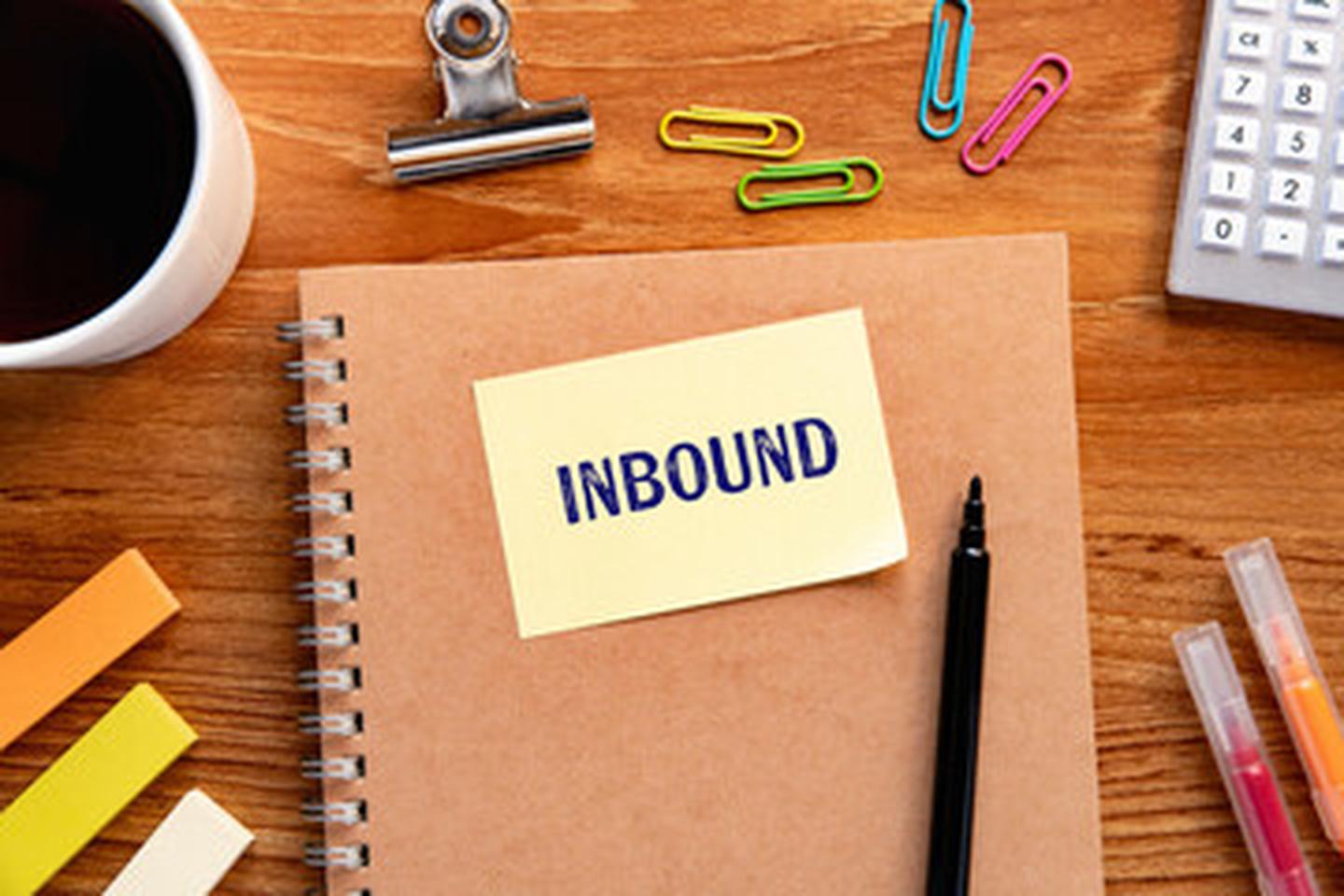column( コラム )
民泊運営の第一歩!許可取得の流れと必要な手続き

民泊を始めるには、適切な許可を取得し、法的に問題のない形で運営することが重要です。許可の種類は、物件の形態や運営スタイルによって異なります。本記事では、民泊運営をスタートするための許可取得の流れと必要な手続きを詳しく解説します。
1. 民泊運営に必要な3つの許可とは?
民泊を運営するには、以下の3つのいずれかの許可が必要です。
(1) 住宅宿泊事業(民泊新法)
✅ 年間最大180日までの営業が可能
✅ 地方自治体への届出が必要
✅ 管理業務を行う場合、住宅宿泊管理業者の届出が必要
(2) 旅館業法(簡易宿所・旅館業)
✅ 年間365日営業可能
✅ 営業許可の取得が必要(保健所の審査あり)
✅ 建築基準法や消防法の適用を受ける
(3) 特区民泊(国家戦略特区)
✅ 特定の地域(東京・大阪など)で運営可能
✅ 自治体ごとに営業日数の制限が異なる
✅ 通常の住宅とは異なる基準が適用される
どの許可を取得するかは、運営するエリアや物件の種類によって決まります。
2. 許可取得の流れと手続き
(1) 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出手順
民泊新法のもとで運営する場合、以下の手続きが必要になります。
✅ 届出先:都道府県・市町村
✅ 主な要件:
- 年間営業日数は最大180日
- 住居専用地域でも運営可能(自治体の条例による制限あり)
- 管理業務は住宅宿泊管理業者へ委託するか、自ら行う場合は届出が必要
✅ 届出の流れ
- 民泊届出システム(電子申請)で申請
- 消防設備の設置・確認(管轄の消防署へ相談)
- 近隣住民への説明・トラブル防止策の実施
- 受理後、民泊施設として営業開始
📌 注意点:
- 各自治体の条例で独自の規制があるため、事前確認が必須
- 180日以上営業したい場合は「旅館業法」の許可が必要
(2) 旅館業法(簡易宿所・旅館業)の許可取得手順
旅館業法の許可を取得することで、年間365日営業が可能になります。
✅ 届出先:保健所(営業許可申請)
✅ 主な要件:
- 客室の最低床面積(3.3㎡以上/人)
- 玄関帳場(フロント)の設置(一部、自治体によって不要)
- 消防設備の設置義務(スプリンクラー・火災報知器など)
- 建築基準法の用途変更が必要な場合あり
✅ 許可取得の流れ
- 保健所へ事前相談(申請要件の確認)
- 建築基準法・消防法の適合確認(自治体・消防署と調整)
- 設備の準備・工事(必要な場合)
- 営業許可申請(保健所へ書類提出)
- 現地審査(保健所・消防署の検査)
- 営業許可取得後、営業開始
📌 注意点:
- 用途地域の規制により、営業不可のエリアもあるため事前確認が必要
- 工事や審査に時間がかかるため、早めの計画が重要
(3) 特区民泊の許可取得手順
特区民泊は、国家戦略特区に指定されたエリアのみで認められる制度です。
✅ 届出先:自治体
✅ 主な要件:
- 宿泊日数の下限あり(例:大阪は2泊3日以上)
- 宿泊者名簿の管理義務
- 近隣住民への事前説明が必要
✅ 許可取得の流れ
- 自治体へ事前相談・申請書類の準備
- 消防設備の設置(管轄の消防署で確認)
- 宿泊者名簿の管理体制を整備
- 自治体の審査を経て、営業開始
📌 注意点:
- 地域ごとに異なるルールがあるため、事前に自治体へ確認することが必須
- 最低宿泊日数が決められているため、短期利用の予約が取りづらい場合がある
3. 許可取得後の運営ルールと注意点
✅ 宿泊者名簿の作成・管理が必須
✅ 近隣住民とのトラブル回避のため、クレーム対応策を準備する
✅ 消防設備(消火器・火災報知機)の定期点検を行う
✅ 行政の立ち入り調査があるため、適切な運営を継続する
特に、違法民泊とみなされると罰則があるため、法令遵守が重要です。
まとめ:民泊運営の許可取得のポイント
📌 住宅宿泊事業(民泊新法):年間180日まで運営可、届出制
📌 旅館業法(簡易宿所):年間365日営業可能、保健所の許可が必要
📌 特区民泊:特定地域のみ対象、自治体ごとのルールを確認
📌 消防・建築基準法・近隣対策などの手続きをしっかりと行う
民泊を適法に運営するためには、どの許可が適用されるかを事前に確認し、計画的に手続きを進めることが大切です。スムーズな許可取得を目指し、安心して民泊事業をスタートしましょう!
Contact
サービス・その他に関するお問い合わせは
リンクフォームからお問い合わせください。