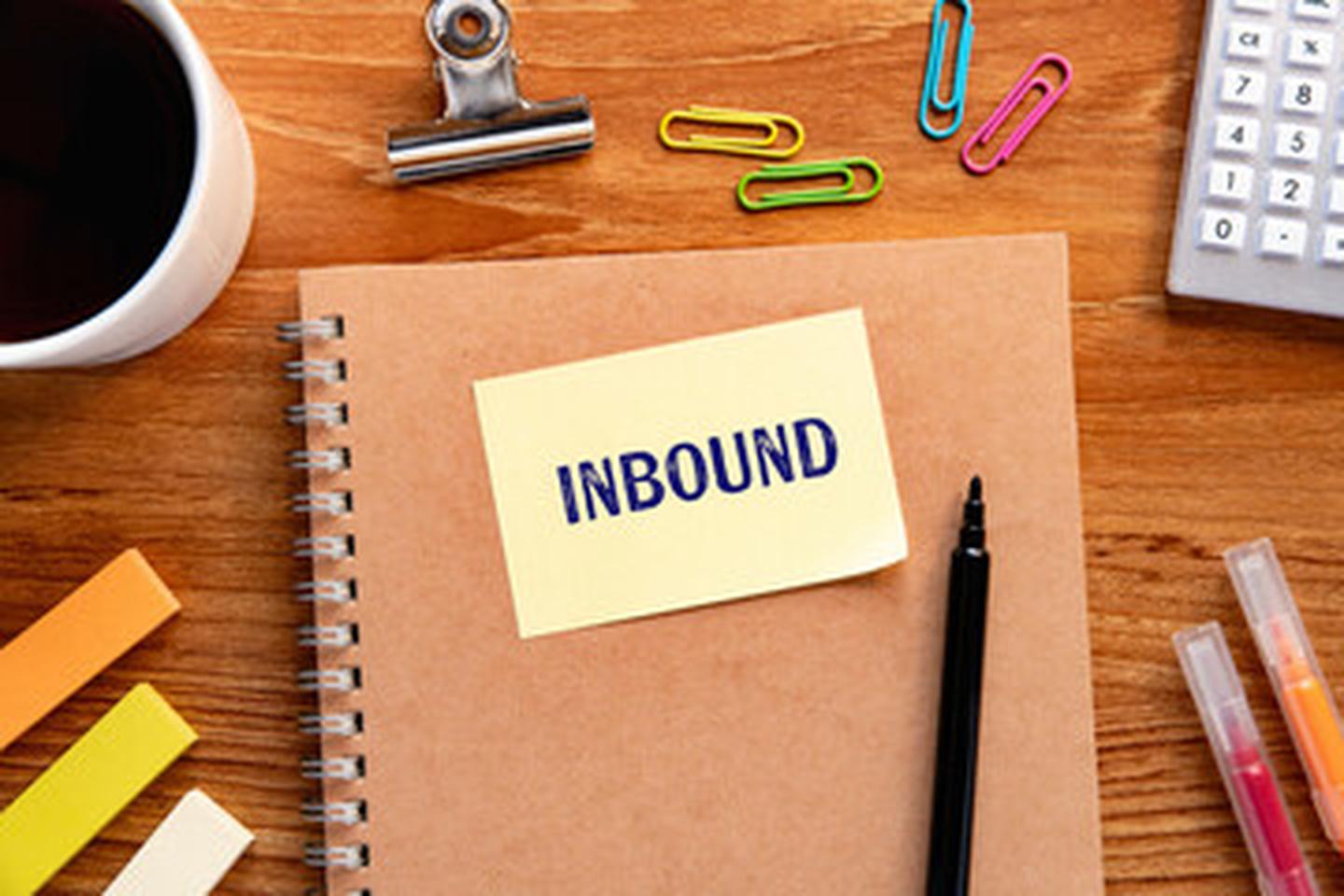column( コラム )
民泊に迫る「オーバーツーリズム」問題──世界と日本の現状から学ぶ持続可能な運営戦略

観光は地域経済を潤す一方で、「観光客が多すぎる」ことによる弊害=オーバーツーリズム(観光公害)が世界中で問題となっています。イタリア・ベネチア、スペイン・バルセロナなど、過度な観光による地域環境や住民生活への影響が深刻化しており、日本の民泊業界にも警鐘を鳴らしています。
今回は、ヨーロッパを中心とした最新の規制動向とともに、日本における民泊運営者がいま取るべき行動について考察します。
世界が直面するオーバーツーリズムの現実
ベネチア──「水の都」の危機
世界遺産都市であるベネチアでは、観光客の集中により、住民人口が70年間で7割も減少。2024年には日帰り客から入場料を徴収する制度を導入し、2025年には徴収日数と金額を拡大。騒音・物価高騰・景観破壊への対応として団体旅行の人数制限や拡声器の使用禁止など、観光規制が強化されています。
スペイン──民泊全廃の動きも
バルセロナでは2028年までに民泊を全廃予定。セビリアでは違法民泊への水道停止措置、バレンシア州では最大60万ユーロの罰金、カナリア諸島では近隣住民の同意を必要とする新制度が進行中。観光による住宅不足や家賃高騰への反発が背景にあります。
欧州各地で進む民泊規制の広がり
- フランス・シャモニーでは2025年5月から民泊を許可制に。
- スイス・ルツェルンでは年間90日間までの貸し出し制限を導入。
- 豪ビクトリア州では2025年1月から民泊収入に対する課税を開始。
これらの動きは、住宅確保と観光業のバランスを巡る世界的な課題を示しています。
日本でも進行する観光公害
京都や鎌倉では、外国人観光客による混雑や騒音、ごみ問題が住民の生活に影響を与えており、観光の在り方が問われています。民泊が地域に密集している場合、騒音や治安問題に発展しやすく、住民との摩擦が発生しやすくなります。
民泊運営者が今からできる3つの対策
① 地域と調和した運営を意識する
ゴミ出し・騒音対策・ルール周知を徹底し、自治体や住民と信頼関係を築く。
② 分散型民泊を推進する
中心部への集中を避け、アクセス可能な周辺エリアへの展開を進める。
③ 短期利益よりも“共生”を重視する
一時的な利益よりも、地域社会との共生を重視することで、長期的な事業の安定が図れます。
まとめ:観光と共に生きる民泊運営を
世界の観光都市が今まさに試されているのは、「持続可能な観光」とは何かという問いです。観光業と地域生活はトレードオフではなく、調和によって共存できます。
TOCORO.では、地域社会と調和する民泊のあり方を追求し、観光の未来を支える運営体制を構築しています。今後の民泊運営においても、“地域とともに成長する”という視点がますます重要になるでしょう。
Contact
サービス・その他に関するお問い合わせは
リンクフォームからお問い合わせください。